歴史と文化
北海道後志地方に位置する赤井川村(あかいがわむら)は、四方を山に囲まれた「カルデラの里」として知られる村です。村名はアイヌ語の「フレ・ペツ(赤い川)」に由来し、村内を流れる赤井川の水が鉄分を多く含み川底が赤く見えたことから名付けられたとされています。古くは良質な黒曜石の産地としても有名で、縄文時代から人々がこの地を訪れ石器の材料として利用しました。明治期になると本州からの開拓者が入植し、1906年(明治39年)に隣接する大江村(現仁木町)から分村して赤井川村が正式に発足しました。開拓初期には新潟県などから移住した農民らにより開墾が進み、一時は人口3,500人近くに達しましたが、その後は農作物の不作や都市への人口流出もあって減少し、昭和期には過疎化が課題となりました。
そんな中、昭和後期の1980年代に村の有志が郷土芸能の創生に取り組み、1981年(昭和56年)に「カルデラ太鼓」という和太鼓の演奏が考案され、翌年には「赤井川音頭」「カルデラ慕情」といった村独自の民謡も作られました。これらは村民の郷土への誇りを表現するものとして誕生し、現在でも地域行事で演奏・披露される伝統芸能となっています。1983年(昭和58年)には第1回「カルデラの味覚まつり」が開催され、郷土芸能の100人踊りが沿道の観客を沸かせました。このカルデラの味覚まつりは毎年夏(8月)に行われる収穫祭で、村の新鮮な農産物や郷土料理を楽しめる一大イベントです。また紅葉の時期の**「メープル街道393もみじ祭」(10月)、新年を祝う「トキワ・ニューイヤーズフェスティバル」(12月)、冬の夜を彩る「シーニックナイト」**(2月)など、四季折々に地域の特色を生かした祭事・イベントが開催され、村内外から人々が集まります。これらの行事は比較的新しく始まったものも多いですが、地域の伝統行事として定着し、村の文化を継承・発信する役割を果たしています。
観光スポット
赤井川村は雄大な自然とレジャーを満喫できる観光資源に恵まれています。最大の目玉は世界的にも知られるスキーリゾートであるキロロリゾートです。村内の朝里岳と長峰岳の山麓に広がるキロロリゾートは、冬季に良質なパウダースノーを求めて国内外から多くのスキーヤー・スノーボーダーが訪れる人気施設です。冬以外のシーズンもゴンドラで山頂まで上がり雄大な景色を眺めたり、マウンテンバイクやカヌー、パラグライダー、ハイキングなど自然を生かしたアクティビティを楽しむことができる通年型のリゾートとなっています。キロロ内には複数のホテルや温泉、飲食店が立ち並び、国際色豊かな観光地として年間を通じ賑わいを見せています。
村の中心部には日帰り入浴施設の**「赤井川カルデラ温泉」**があります。泉温46℃の天然温泉で、無色透明ながら塩分や炭酸水素を含む湯は肌あたりが良く「美人の湯」として親しまれています。露天風呂からは周囲の山々を望み、カルデラ盆地ならではの開放的な景観を楽しみながらゆったりと疲れを癒やすことができます。利用料金も手頃で村民のみならず観光客にも人気のスポットです。
自然景観では、赤井川村独特のカルデラ地形を一望できるビューポイントが各所にあります。村を囲む外輪山の一つ、冷水峠(れいすいとうげ)展望所は標高約700mの地点にあり、360度山に囲まれた盆地全体を見渡せる絶景スポットとして知られます。早朝には霧が盆地に立ち込めてまるで雲海の湖のような幻想的風景が現れることもあり、写真愛好家にも注目されています。晴天時には遠く羊蹄山や積丹半島まで望める景勝地で、ドライブで訪れる観光客も多くいます。秋には国道393号線沿いが紅葉で彩られ、「メープル街道」と呼ばれるドライブコースとして人気です。
その国道沿いにある**道の駅「あかいがわ」**も見逃せません。2015年にオープンした北海道で115番目の道の駅で、カルデラ盆地の玄関口・常盤地区に位置します。敷地内では地元産の新鮮野菜や果物、加工品、お酒など赤井川村ならではの特産品が販売され、旬の味覚を目当てに訪れる人々で賑わいます。ここでは赤井川産の牛乳や野菜を使ったジェラートも人気で、ドライブの休憩がてら特産グルメを味わうことができます。また道の駅には観光案内所も併設されており、村内観光スポットのパンフレットや情報提供を受けることができるため、旅の拠点としても便利です。
そのほか、村内には牧場での食体験やレジャー施設も点在します。山中牧場は赤井川産の生乳を使ったソフトクリームやバターで有名な観光牧場で、濃厚でさっぱりした絶品ソフトクリームを求めて遠方から訪れる人もいます。牧場の緑豊かな風景の中で放牧牛を眺めながら味わうスイーツは格別です。さらに農業体験のできる観光農園や季節ごとの収穫体験イベントも行われており、都市部では味わえない田舎ならではの楽しみを提供しています。例えば毎年9月には**「まるっとカルデラ農村フェス」**と題した収穫祭イベントが開催され、地元産トウモロコシのもぎ取り体験や農産物直売、夜には花火大会なども催されます。雄大な自然と農村文化を生かした観光スポットが多彩に揃う赤井川村は、「日本で最も美しい村」連合にも加盟しており、四季折々の景観美と素朴な村の魅力で訪れる人々を魅了しています。
農業・特産品
赤井川村の基幹産業の一つは農業であり、「北海道で栽培できる農作物は何でも作れる」と言われるほど多種多様な作物が生産されています。カルデラ盆地特有の豊かな土壌と昼夜の寒暖差の大きい気候が、高品質な農産物を育むのに適しているためです。主要な作付品目としては、お米やジャガイモのほか、カボチャ、ブロッコリー、ミニトマト、カラーピーマンといった野菜類が挙げられます。特にカボチャはホクホクとした食感の「味平(あじひら)」カボチャが多く作られ、天ぷらや煮物にして絶品だと評判です。近年では畑地灌漑設備の整備やビニールハウス栽培の増加により、通年安定して野菜を出荷できる体制が整い、野菜栽培の比率がさらに高まっています。また花き栽培にも取り組んでおり、切り花用のユリやトルコギキョウなども施設栽培されています。
果物の生産も村の自慢で、メロンやスイカ、トウモロコシといった甘みの強い作物が人気です。赤井川産メロンは赤肉メロンの優良品種をハウスで丁寧に育てており、糖度が高く香り豊かで市場でも高く評価されています。夏にはスイカも栽培され、みずみずしく濃厚な甘みがあると好評です。中でもトウモロコシは赤井川村を代表する特産の一つで、砂糖並みに甘い新品種がいち早く導入されてきました。例えば「グラビス」というバイカラー(黄白の粒)品種は、その甘さがメロンなど果物に匹敵すると謳われ、生でも食べられるほど糖度があります。「ミエルコーン」(※フランス語で蜂蜜の意)や「ゆめのコーン」など名前からして甘さを感じさせるトウモロコシも栽培されており、収穫期には朝採れとうもろこしを目当てに道の駅に行列ができるほどです。
こうした農産物を活かした加工品やブランド化戦略にも力を入れています。道の駅「あかいがわ」で販売されている**「赤井川ジェラート」は、村産の牛乳や季節の野菜・果物を使ったジェラートで、住民のアイデアから生まれたヒット商品です。例えばカボチャやトウモロコシ味のジェラートは素材の風味が濃厚でここでしか味わえないと評判になっています。また、赤井川の新鮮野菜を使ったスープやカレー、ジャムなどの加工食品も開発されており、村おこしの特産品として通信販売やふるさと納税の返礼品にもなっています。中でも山中牧場の発酵バター**は全国的なグルメコンテストで1位に輝いた経歴を持つ逸品で、濃厚で香り高い味わいが人気です。そのバターを使った焼き菓子や牛乳を用いたスイーツなど、農畜産物の付加価値を高める取り組みが盛んです。
赤井川村ではブランド豚「四元豚(よんげんとん)」の飼育や地元産卵を使ったスイーツ開発など、新たな特産品づくりにも挑戦しています。さらに農業体験や収穫祭イベントを通じて、自慢の農作物をPRする機会を設け、観光客にも「カルデラの恵み」を味わってもらう工夫を凝らしています。このように第一次産業と地域ブランド戦略を結びつけることで、農産物そのものだけでなく加工品や体験プログラムを含めた総合的な地域の魅力発信に努めているのが特徴です。
人口・地理・気候
赤井川村の総面積は約280平方キロメートルで、その大部分が山林です。村域の北西部に直径約6kmのほぼ円形のカルデラ盆地(赤井川カルデラ)が広がっており、この平坦な盆地部分に集落や農地が集中しています。外輪山に囲まれ南側が切れた地形で、盆地を貫流する赤井川が南へ流れ出して隣町へと注いでいます。標高1,000~1,400m級の山々に囲まれているため東西南北いずれの方向へも峠を越えて出入りする地勢で、村の東側は札幌市南区との境界に余市岳(1,488m)が聳え、北は余市町との境に大江山(1,058m)、南は倶知安町との境に本倶登山(1,046m)などがあります。これら山地のおかげで外から隔絶された静かな環境が保たれており、「北海道唯一のカルデラ盆地」という珍しい地形景観が赤井川村のシンボルになっています。
気候は典型的な内陸性の気候で、夏は比較的気温が上がり暖かい一方、朝晩との寒暖差が大きくなります。真夏日になる日もありますが、夜間は涼しく過ごしやすいため、トマトやスイカなどは糖度が上がり美味しい作物に育ちます。秋は早く訪れ、盆地を取り囲む山々が一斉に紅葉する様子は圧巻です。冬は北海道内でも有数の豪雪地帯として知られ、積雪は村の平地部でも最大で1.5~1.7メートルにも達します。毎日のように雪かきが必要なほど降りますが、その反面パウダースノーの上質な雪質はスキー場に恩恵をもたらし、村に冬の観光客を呼び込む資源ともなっています。役場では十分な除雪体制を整えており、生活道路の確保には力を入れています。春は雪解けが遅く4月頃まで残雪がありますが、遅い春の訪れとともに畑作の準備が始まり、5月には新緑と山桜が一斉に芽吹いて短い夏への期待が高まります。
人口は戦後長らく減少傾向にありましたが、近年は下げ止まりつつあります。2020年(令和2年)の国勢調査では1,165人で、道内179市町村中でも下位の規模ですが、その後移住促進策や観光産業の影響もあってわずかな増加に転じ、2025年6月末時点での人口は約1,230人となっています。高齢化率が高い点は他の農村部と共通する課題ではあるものの、札幌圏に比較的近い立地や子育て支援の充実などから若い世代の転入も見られるようになりました。人口密度にすると約4人/平方kmほどで、広大な土地に少数の人々が暮らす過疎地域ですが、その分豊かな自然環境とゆったりした暮らしが維持されています。札幌市中心部から車で1時間強、小樽市からは約30kmとアクセス圏内にあることから、将来的にも利便性を活かした定住人口の確保が期待されています。
教育・インフラ
赤井川村には村立の義務教育学校として小学校と中学校があります。2025年現在、小学校は赤井川小学校および都(みやこ)小学校の2校がありますが、児童数減少に伴い都小学校は2026年春に閉校し赤井川小学校に統合される予定です。これにより村の小学生は全員が一つの学校に通うことになり、きめ細かな複式学級教育が引き続き行われます。中学校は赤井川中学校が1校あり、小中学生全体でも数十名規模の小さな学校です。少人数だからこそ教師と生徒の距離も近く、一人ひとりに目が行き届いた教育が行われています。また、村では国際感覚を養う教育にも力を入れており、中学生を対象にオーストラリアへの海外研修を行う独自のプログラムがあります(費用は村が負担)。小・中学生の給食費も全額無料となっており、経済的負担を気にせず安心して義務教育を受けられる環境が整えられています。
医療面では、村内に赤井川診療所という村立の診療所があります。常勤医師がおり、主に内科診療と軽度な外傷の処置、健康相談などを担っています。診療所は平日日中のみの開設ですが、高齢者の往診や予防接種など地域医療にも貢献しています。大きな病院はありませんが、隣接する余市町や小樽市には総合病院があり、車で30~60分ほどでアクセスできます。村では医療機関への通院が必要な高齢者向けに送迎支援も行っており、緊急時にはドクターヘリの要請体制も確保しています。日常の買い物に関しては、村内にコンビニエンスストアはありませんが、小規模な商店やAコープ(農協系のスーパー)が営業しており、生鮮食品や日用品の入手は可能です。生協の移動販売車も定期的に巡回しており、買い物弱者への配慮もなされています。インターネットは全域でブロードバンド回線が利用可能で、テレワークなども問題なく行えるインフラが整っています。
交通インフラについては、鉄道が通っていないため自家用車が移動の基本になります。主要道路は小樽方面と倶知安方面を結ぶ国道393号線(愛称:メープル街道)で、冬季も除雪が行き届き比較的走行しやすくなっています。また札幌方面へは余市岳を避けて国道経由で小樽市内に出てから高速道路を利用するルートが一般的です。かつては路線バス(北海道中央バス)が村中心部と小樽市を結んでいましたが、利用者減少により2022年に廃止されました。現在は村が主体となって**「むらバス」**と呼ばれるコミュニティバスを運行しており、キロロリゾート~都地区~村役場周辺~冷水峠~JR余市駅間を結んでいます。村民の足として平日・土日に運行し、スクールバスも兼ねることで効率化を図っています。この取り組みは全国的にも評価され、ふるさと納税サイトの地域貢献賞を受賞するなど、過疎地交通のモデルケースとして注目されています。道路網については、村内を横断する主要地方道が1本あり、冬でも集落間の移動は可能です。各家庭では冬用タイヤや除雪機の備えが必須となりますが、村全体で助け合いながら厳冬期を乗り越えています。
行政サービスの面では、小規模な村ながら住民に寄り添ったきめ細かな対応がなされています。役場には総合窓口が設置されており、住民票や税務手続きのほか、高齢者福祉や子育て相談など幅広く対応しています。高齢者向けにはデイサービスセンターや**シルバーハウジング(高齢者世話付住宅)**が整備され、地域包括支援センターが介護や生活支援の相談に応じています。また、防災面では全世帯に防災無線端末を配布し、火災や災害時にはサイレンや無線放送で速やかに周知が行われます(毎月8日には1966年の赤井川大火を教訓とした防災サイレンが鳴らされ、防火意識の啓発を続けています)。このように教育・医療・交通・行政の各インフラは都市部ほど充実してはいないものの、村民が安心して暮らせる最低限かつ実用的な体制が整えられており、小さな村らしい機動力で住みよい環境づくりが進められています。
移住・暮らし
近年、赤井川村は移住先としても注目され始めています。自然豊かな田舎暮らしが楽しめる一方で、札幌圏への通勤圏内という利点や、村独自の手厚い移住支援制度が評価され、北海道内の移住支援策充実自治体ランキングでも上位に取り上げられました。村では2016年(平成28年)から**「移住・定住支援事業」を本格的に開始し、定住人口の増加と地域活性化を図っています。その柱となっているのが住宅取得支援で、村内に住宅を新築して10年以上定住することを条件に最大300万円の建設費補助**を受けられる制度です。対象は自ら居住する持ち家のほか、店舗併用住宅やアパートなども含まれ、多様なライフスタイルに対応しています。さらに、新築後3年間は固定資産税を半額免除する優遇措置もあり、マイホーム志向の移住希望者には大きな後押しとなっています。
賃貸派の方向けにも魅力的な施策があります。村営の定住促進住宅では、一定期間(例えば25年間)継続居住すると住宅と土地の所有権が無償譲渡される仕組みを導入しています。具体的には、家賃月額4万円程度で新築の一戸建て住宅に住み始め、長期にわたり定住した世帯にはその住宅をそのまま「自分の家」として持てるという画期的な制度です。また、村内の空き家情報を集めた空き家バンクも運用しており、古民家を含む売買・賃貸物件の紹介や改修費用の一部補助なども行っています。移住希望者が住まいを確保しやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる点は、赤井川村の大きな魅力です。
子育て世代に対するサポートも非常に充実しています。前述のように中学生まで医療費完全無料化・給食費無償化が実施されているほか、へき地保育所(村立保育園)は利用料が全額無料で提供されています。妊娠期から出産にかけても支援があり、妊婦健診や出産のために札幌・小樽方面の病院へ通う際の交通費・宿泊費の補助、出産時にはお祝い金の支給といった制度があります。結婚に際しても結婚祝金が用意され、新婚世帯には国の制度に上乗せする形で住宅取得や引越し費用の助成(結婚新生活支援事業)もあります。さらに、村独自のユニークな特典として、村民はキロロスキー場のシーズン券が無料でもらえる制度があります。ウィンタースポーツ好きの移住者にとっては嬉しいメリットであり、家族でスキーやスノーボードを気軽に楽しむことができます。
就労面では、農業に新規参入したい人へのサポートや、地域おこし協力隊の受け入れにも積極的です。実際に「都会での仕事を辞めて移住し、地域おこし協力隊員として活動しながら農業を学んでいる」若者や、「子育て環境を求めて移住し、有機野菜の農園を経営するようになった」家族など、移住者の成功事例が少しずつ増えてきています。移住者からは「夜は満天の星空が広がり、スマホの画面ではなく本物の自然を眺める豊かさに気づいた」「子どもを伸び伸びと遊ばせられる」「地域の人が皆顔見知りで温かく迎えてくれる」といった声が聞かれ、都会にはない暮らしの魅力を実感する人が多いようです。村も移住相談会への参加や、お試し移住体験住宅の提供などを通じて積極的に情報発信し、「人と自然が育む美しい村」で新生活を始めたい人を応援しています。
生活環境については、自然に囲まれていながら日常生活に必要なサービスは概ね利用できます。自家用車があれば週末に小樽市街地へ買い出しに出ることも容易で、逆に都市部の喧騒を離れてスローライフを満喫できる点が魅力です。季節ごとの自然の恵みも豊富で、夏には家庭菜園で野菜作りを楽しんだり、秋には山菜やキノコ採り、冬はスキーやスノーシューで雪遊びと、アウトドア派にも嬉しい環境です。村内には地域コミュニティも健在で、消防団や祭りの実行委員などに若い移住者が参加するケースも増えており、「よそから来た人」でもすぐに顔見知りができて溶け込める風土があります。人口は少ないながらも、そんな村民同士の助け合い精神と外からの新しい風が融合し、赤井川村はゆるやかにではありますが活気を取り戻しつつあります。
以上、歴史・文化から観光、産業、暮らしに至るまで赤井川村の特徴を網羅的にご紹介しました。カルデラの大地に育まれた美しい景観と人情味あふれるコミュニティを併せ持つ赤井川村は、小さいながらも輝きを放つ北海道の宝石のような存在です。近年はその魅力が見直され、観光客や新しい住民との出会いによってさらに豊かな村づくりが進んでいます。豊富な自然の恵みと温かな人々に囲まれた赤井川村は、訪れる人にも住む人にも「また帰ってきたい」と思わせる不思議な魅力を備えた村と言えるでしょう。
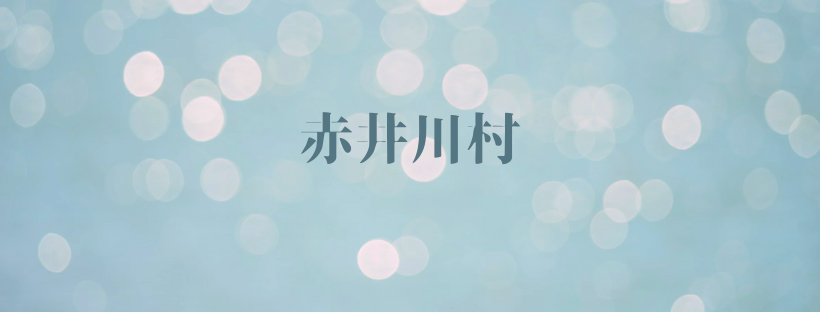
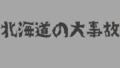
コメント